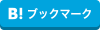執筆協力 編集室システムU okamura.nobuyoshi@gmail.com
谷津矢車さんが人物と周辺を語る
2025 年のNHK大河ドラマは「べらぼう~蔦重栄華之夢噺~」。江戸の版元として喜多川歌麿を見いだし、東洲斎写楽を世に出した蔦屋重三郎の半生を追う。その見どころを、『蔦屋』の著書を持つ青梅市在住の作家・谷津矢車さんが語る。 (岡村繁雄)
.jpg)
『蔦屋』(文春文庫)
谷津さんが、蔦屋重三郎を主人公に『蔦屋』(文春文庫)を描いたのはおよそ10年前のこと。そのころ、蔦屋を取り上げた作品はそれほど多くはなかったという。とはいえ、その存在感は谷津さんの執筆意欲を刺激した。

「彼には文化の守護者という顔があり、一方で新しいものを手がける前向きな面もある。版元は黒子に徹する者が多いが、蔦重は違う。みずからが前に出て、蔦屋をブランド化し草紙や浮世絵を売っていく。そんな現代のプロデューサー的な生き方は興味深い」
重三郎活躍の背景として、江戸時代中期、宝暦・天明年間という時代を見逃すことはできない。この時期、幕府老中の田沼意次が行った商業を重視する政策によって町人文化が栄えたのである。江戸の町に金が回り、庶民が活躍する様子を若手俳優中心のキャストが演じる。
「蔦屋には、何人もの戯作者や絵師が集まった。そこには、彼らを誘う磁場があったのかもしれない。例えば、幕府の禁令を犯して処罰された山さんとう東京きょうでん伝。重三郎は彼が失意のとき、はじめて稿料を出すことで再び筆を執らせている。作家の個性や江戸の人々のニーズに応じてヒットを連発させた」
そう話す谷津さんは、最新作『憧あくがれ写楽』(文藝春秋)で謎の浮世絵師に挑む。大胆にデフォルメされた役者の大首絵が人気になったにもかかわらず、わずか10カ月で忽然と姿を消してしまう。蔦屋重三郎は、なぜ写楽の正体を隠したのか……。谷津さんの作品では、これまで誰も指摘したことのない意外な人物を明らかにしていく。
 シェア
シェア ポスト
ポスト LINEで送る
LINEで送る